
[読書] 河野稠果『人口学への招待』(中公新書 2007年8月)
(挿絵は、やはりアルテミス像。ただし、ギリシア神話の古い層を表しているといわれるエペソス地方の像。多数の乳房が多産の守り神を表現しているのか。)
今書いているのは、あくまで、河野氏の本を読んで私が考えたことである(念のため)。今日は、「合計特殊出生率」の話に入る前に、まず「総出生率」と「完結出生児数」との発想の違いを考えてみたい。前回見たように、出生率は分母に何をもってくるかが大きな問題である。総人口よりは、15〜49歳の女性を分母にする方が、「出産数を規定する実際の条件」により近いものを母集団にすることになる。総人口が同じでも、その人口ピラミッドの形が違えば、出産可能な女性の数は大きく変わるからである。こうして、「粗出生率」ではなく、15〜49歳の女性を分母にもってくる「総出生率」という概念が成立する。
しかし、ここで立ち止まって、もう一度「出生率」とは何なのかを考え直してみなければならない。「この50年間に出生<率>はどう変化したか」という問いは、「この50年間に出生<数>はどう変化したか」という問いとは違う。後者は、たんに数えればすむ話である。だが、「出生率」という概念は決して自明ではない。「産むことのできる女性が、どれだけ実際に産んだか」を示す「率」が、「出生率」なのだろうか。しかし、「産むことのできる女性」とは何を意味するのか? 出産可能な身体を持っている性が「女性」の定義なのだろうか? もしそうならば、「産むことができる女性」というのは「女性」というのとほとんど変わらない。現に、総人口を分母にもってくる「粗出生率」は、総人口の半分が女性だから、女性全員を分母にするのと同じ発想である。それに対して、分母を15〜49歳という年齢に限定することによって、「産むことのできる女性」という概念を、より現実的に狭く取ったのが、「総出生率」である。
そのポイントは、「出生率を算出する当該年度に、15〜49歳である」女性という点にある。この前半は見落とされがちだが、「出生率」が「ある年における」出生率であることは、けっして当たり前のことではないのである。というのは、出産というのは、徹底的に個人的な営みだからである。「産むことのできる女性が、どれだけ実際に産んだか」を示す値は、その女性が産み終わってみなければ分からない。ある特定の年ではなく、その女性が少なくとも49歳くらいまでの年齢に達したときに初めて決まる値なのである。だから、未婚の女性も含めて「ある年度に15〜49歳の女性」を、「その年度において、産むことのできる女性」として分母にもってくる「総出生率」は、ある特別な仮定にもとづいている。それは、「ある年に15〜49歳である全女性」を、あたかも一人の女性が15歳から49歳までを生きる時間的流れであるかのようにみなす虚構である。「出生率」はしばしば、「一人の女性が一生の間に産む子供の数」というように説明されるが、この説明には大きな飛躍があるのである。
「産むことのできる女性が、どれだけ実際に産んだか」と言うときの、「産むことのできる女性」とは何を意味するか、さらに考えてみよう。15〜49歳という年齢は生物学的制約としての「産むことのできる」をおおよそ規定するものであろうが、しかし出産は、女性が「産む意思」や、「産むための経済的条件」を持たなければ現実化しない。だから、「産むことのできる女性」とは、本来、「産むことのできる生物学的条件を持ち、かつ、産む意思と、産む経済的条件を持つ女性」でなければならない。だが、「出生率」の分母にくる「産むことのできる女性」はそうなっていない。独身女性あるいは学生などもすべて含んでおり、「産む意思や経済的条件」はまったく考慮されていない。結婚するつもりのない女性、結婚しても産むつもりのない女性なども、すべて分母に数えている。つまり、「出生率」という概念は、それ自体がかなり「押し付けがましい」ものだということが分かるだろう。「産むことのできる女性」というその「できる」に、本人の意思や置かれた条件を一切考慮していないからである。それにもかかわらず、そうしたマクロな統計数値を「一人の女性が一生の間に産む子供の数」のように説明することは、出産という完全に個人的な営みに対して、国家的な人口政策の視点を投影することになるのである。
ところで、未婚者を含む「産むことのできる女性」一般ではなく、「産むことのできる生物学的条件を持ち、かつ、産む意思と、産む経済的条件を持つ女性」を分母にとって出生を捉える視点も、もちろん存在する。それが、「完結出生児数」という統計である。それは、結婚して15〜19年たった夫婦が実際に生んだ子供の数である。「結婚して15〜19年たった夫婦」と「産むことのできる生物学的条件を持ち、かつ、産む意思と、産む経済的条件を持つ女性」とは決して同一ではないが、長期間結婚が持続したという事実は、ある程度こうした条件を満たすと考えてよいだろう。以下がそれである。
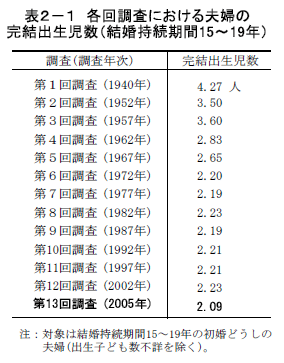
ここから分かるように、結婚した夫婦が実際に産んだ子供の数は、1972年から2005年までの30年以上にわたってほとんど変化していない。にもかかわらず、この30年、日本は「出生率が大きく下がった!」と大騒ぎしてきた。その理由はどこにあるのだろうか。もちろん、統計的には「完結出生児数」もこれからは今までよりは低下するものと思われる。晩婚になれば、産める子供の数が結果として減るからである。しかし、独身者まですべて分母にとった「総出生率」や「合計特殊出生率」と違って、「完結出生児数」は、ある時点のマクロ統計を一人の女性の人生のごとくみなすという虚構を含んでいないので、出生率という概念を批判的に考察する際にとても重要なのである。[続く]