[今日の絵] 5月前半

1 ヘンドリック・ステーンウェイク : アーヘンの市場広場
街には人がただ存在するのではなく、街で人は生きている、街の絵には必ずその生きざまが描かれ、画家がたくさん「街」を描くのは、そこにいる「人」を描きたいからだ、作者は17世紀オランダの画家

2 Francesco Guardi : サン・マルコ広場1760年代
フランチェスコ・グアルディ1712-93はイタリアの画家、ヴェネチアの都市風景をたくさん描いた、この絵も、広い空など遠近法が見事で、描かれた人々も生き生きとして活気がある

3シスレー : アルジャントゥイユの広場(ショッセ通り)1872
アルジャントゥイユはパリ北西10キロの所にある、アベラールとエロイーズの恋で有名な町、モネ、ルノワール、シスレー、カイユボット等多くの画家が住み、郊外、川、橋など含めてたくさん描いた、どの絵も空が明るく美しい

4ムンク : 春の日のカール・ヨハン街1890
「カール・ヨハン街」はオスロの目抜き通り、街は光に溢れているが空はやや暗い、通りの両側にびっしり人が並んでおり、手前の人たちはそこに向かって歩いているのか、手前の人たちは女性の後ろ姿ばかりなのはなぜ

5 Pissarro : Rue Saint-Honoré in the Afternoon. Effect of Rain 1897
「サン=トノレ通り」はパリの中心街、午後の雨上がり、正面の建物1階の角はカフェだろうか、ピサロの描くパリの街はいつも端正で、人も含めて美しい

6 Theodore Butler : Place de Rome at Night 1905
セオドア・バトラー1861-1936はアメリカの画家だが、生涯の大部分をフランスで活動、モネと親交があった、この絵は「夜のローマの広場」と題されており、雨上がりなのか、まるで海上の舟の明りのよう美しさ

7 Maurice Prendergast : The Grand Canal, Venice 1899
モーリス・プレンダーガスト1858-1924はアメリカの画家、モザイクのような色彩で都市をたくさん描いた、この絵は、運河も道路も混みあっていて、活気がある

8 Bernard Boutet de Monvel : ヌムールの寄宿学校 1909
ベルナール・ブーテ・ド・モンベル1881-1949はフランスの画家、彫刻家。これは、フランスの都市ヌムールの街を歩く寄宿学校の生徒たちと先生。空、家々、並木、枝先、緑地、先生生徒の黒い服装などがよく調和している

9 Alson Skinner Clark : Panama City Plaza 1913
アルソン・スキナー・クラーク1876-1949はアメリカの画家、明るい光に溢れた風景をたくさん描いた、これはパナマ市にある広場らしいが、人々の賑わっている感じがよく描かれている、人々はただ歩いているのではなく何かしている

10 Konstantin Korovin : パリ 大通り1939
コンスタンティン・コロヴィン1861-1939はロシア印象派の画家、パリの夜の街もたくさん描いた、建物から漏れる光と路面での光の反射の融合が美しい、この絵は空が明るいのもいい

11 Jeremy Mann : New York City 2016
ジェレミ・マン1979~は現代アメリカの画家、夜の光の点滅する感じが素晴らしく、ニューヨークなど現代都市の雰囲気が見事に描かれている

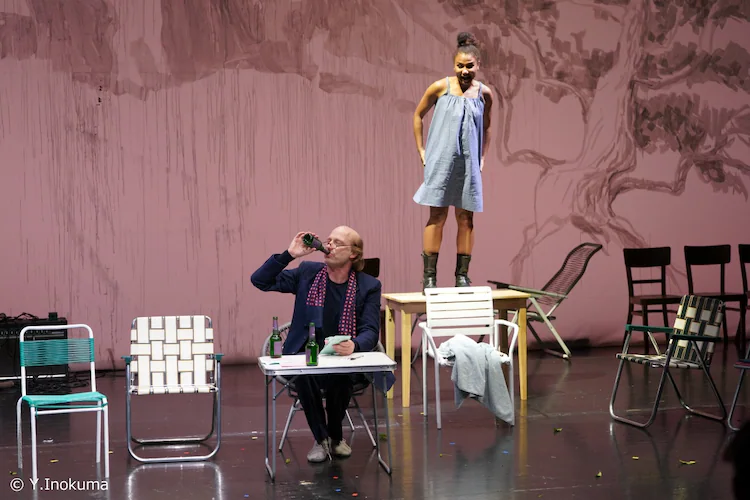


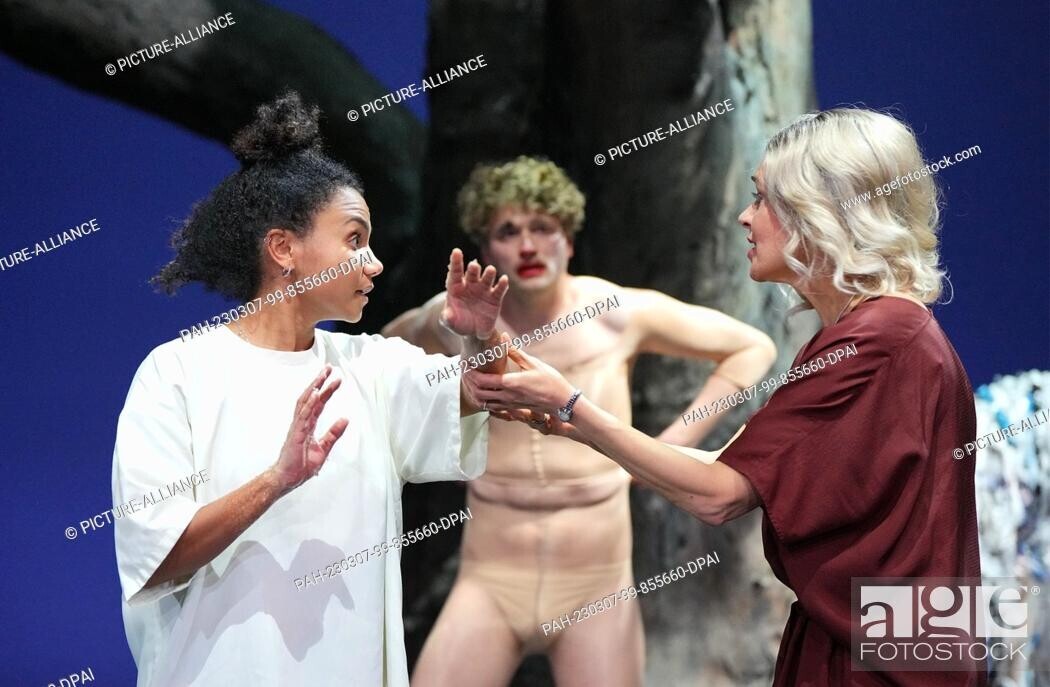




 デカローグ3は、妻と子どもと愛のあるささやかな家庭をもつタクシー運転手だが、クリスマスイブに元愛人が突然やってきて、困惑する。妻子に知られないように、そして元愛人も傷つけないように、彼は誠実に対応するが、元愛人も孤独で大きな嘘をついたりして二人の亀裂は深まるが、最後には和解。誰にでもありそうな話で、とてもリアル↓。
デカローグ3は、妻と子どもと愛のあるささやかな家庭をもつタクシー運転手だが、クリスマスイブに元愛人が突然やってきて、困惑する。妻子に知られないように、そして元愛人も傷つけないように、彼は誠実に対応するが、元愛人も孤独で大きな嘘をついたりして二人の亀裂は深まるが、最後には和解。誰にでもありそうな話で、とてもリアル↓。















