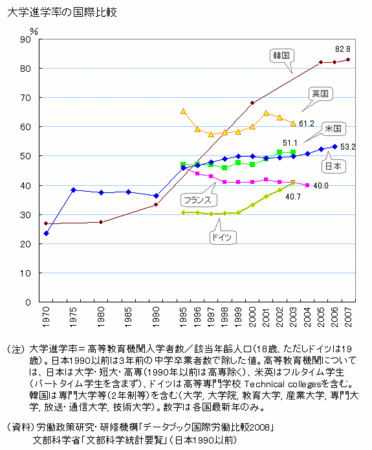[読書] 吉川徹『学歴分断社会』 (ちくま新書、09年3月刊) [続き]
(写真は著者近影、著者のブログは http://kikkawa.blog.eonet.jp/default/ )
[承前] 著者は、三浦展氏の『下流社会』(2005)の論点を踏まえながら、「下流」問題を「学歴分断線」の視点から再解釈する(本書第6章)。その際の論拠となるデータは、社会学者による大規模な共同研究「2005年SSM調査(社会階層と社会移動全国調査)」その他である。まず重要な一点であるが、「自分を下流だと思う人」が増えているわけではない。「自分をどの階層だと思うか? 上、中の上、中の下、下の上、下の下、のどれ?」という問いに対する答えは、30年間まったく変わっていない。p159のグラフは驚くべきものだが、1975年以降の30年にわたる調査で、2006年に「下の下」と「下の上」がほんの僅かだけ増えているが、実質的にはグラフは30年間まったく不動のままである。経済の面では、高度成長終了後、バブル期、氷河期と色々あったはずなのに、あるいは、マスコミで「下流」や「格差」が喧伝される割には、自己の属する階層意識はまったく微動だにしていない。つまり、自己意識についてのマクロ統計からは、「総中流社会から格差社会へ!」とは簡単に言えないと著者は主張する。
だが、「下流」を自己意識ではなく、学歴や収入という実体的な数値から捉えてみたらどうか? SSM調査で自分を「下流(=下の下、下の上)」と答えた37.4%(この数値は三浦氏の調査ともほぼ一致)を、大卒/非大卒、雇用の正規/不正規、世帯収入550万円以上/以下という軸で分類する。すると、「下流」の学歴別は、大卒が30%、非大卒が70%になる。その非大卒70%の内訳は、「非大卒・低収入・非正規」が32%、「非大卒・低収入・正規」が23%で、合計で全体の55%を占める。要するに、自分を「下流」と意識する人は、その理由として、非大卒や低収入という実体的な裏づけがあることが分かる。
上の調査は、三浦展『下流社会』に合わせて、35歳以下の若者を母集団に取ったものだが、平成になってから社会人になった40歳以下の男女をサンプルに取ると、さらに大きな母数をもとにした分析ができる。それがp172の以下の図である。
(高収入・正規)(高収入・非正規)(低収入・正規)(低収入・非正規・・)( 計 )
(大卒) 211人 103人・・ 126人・・・ 91人・・・ 531人
(非大卒・・) 203人 96人・・・・ 288人・・・ 206人・・・ 793人
( 計・・・・) 414人 199人・・・・・・・・ 414人・・・ 297・・・人 1324人
この図では、「収入の高低」といっても550万円で分けただけの大まかなものだが、それでも、「低収入」者の7割、「低収入・非正規」者でも7割が非大卒である。明らかに非大卒と低収入には大きな相関関係がある。さらにまた、このSSM調査によれば(p174f)、「クラシック音楽のコンサートに行く頻度」のような、ブルデューのいう「文化資本」がものをいう項目では、「大卒・高収入」と「非大卒・低収入」に有意の差が見られるが、むしろ重要な問題として、「選挙に投票に行く頻度」が、「非大卒・低収入」は明らかに低い。また支持政党では、公明党の支持率が非大卒は大卒に比べてかなり高い。とりわけ低収入・非正規者では大卒の公明党支持者がゼロであるのに、非大卒では10%近い。収入とはほぼ無関係に、非大卒と大卒では、公明党支持に大きな違いがあるのだ。
大卒と非大卒という分類から導かれるデータはまだ色々あるのだが、モンスターペアレントについての考察もユニークだ(p180f)。著者は、モンスターペアレントは大卒と非大卒との「双頭竜」だと言う。というのも、そもそも小中学校に親が要求するものが、初めから両者で大きく異なるからである。もちろん、非常識なモンスターペアレントへの対応は、弁護士やカウンセラーの仕事であろうが、モンスターペアレントが登場する背景には、学校への親の要求の二極化がある。「子供にはできるだけ高い教育を受けさせた方がよいか?」という質問に、大卒の父母は76.9%が「イエス」と答えたのに対して、非大卒層では47.4%しかそう答えていない。大卒父母は、「しつけはなるべく家庭で」と考える人が多いが、非大卒はそうでもない。「小中学校を進学塾とみるか、託児所とみるかということが、親の学歴によって二極化している」(p184)。だから、どちらから見ても学校の現状には不満で、文句を言う親が現れやすいのである。
「双頭竜」だけでなく、著者は名前の付け方が巧い。たとえば大学卒の母親は「ヴィーナスの腕の効果」を持つという(p142f)。「母親が大学卒」であることは、「父親が大学卒」とは違う意味があるのだ。たとえば、子供の立場からすると、「一流大学を出ているけれど年収は350万円のサラリーマンを父親に持つ場合と、高卒だが年収1000万円の自営業主を父に持つ場合では」(p145)、どうみても後者の方が「よい父親」だろう。だが、母親はたとえ収入ゼロの専業主婦であったとしても、大学卒の学歴は色あせない。それは彼女が「もし仕事の世界で、その能力を余すところなく発揮していれば、どのような可能性をもっていたか」(同)を表すものだからである。ミロのヴィーナスの失われた腕が、そこにあったはずの可能的な美しい腕を我々に想像させるように、大学卒の母親は「ありえたはずの有能な私」を心に描き、子供の教育にもそれだけ熱心である(ちなみに、これは私事だが、私(=charis)の妹は東大卒の専業主婦なので、吉川氏の言うことはよく分かる)。また、教育学者の本田由紀氏の研究によっても、母親が大卒であるか否かが、その家庭の教育の質を大きく左右しているという(p147)。
このように、本書は興味深い論点に満ちているが、私が一つだけ判断を留保したいと思うのは、今後ともずっと大学進学率が50%強で止まるのかどうかという点である。大学進学率が、その国の歴史、制度、文化、政策などに大きく影響されていることは事実である。だが各国の大学進学率の比較である下図を見ても、20〜30年単位の先の予測は困難ではないだろうか。50%の「ガラスの天井」が本当にあるのかどうか、韓国の例などみても、何とも言えないように思われる。[終]