
[読書] 吉川徹『学歴分断社会』(ちくま新書、09年3月刊)
(下図は、大学進学率の変化。1960〜75年に大きく上昇したが、その後はゆるやかな変化であり、50%前半で頭打ちになると予想される。90年頃は18歳人口が多いので進学競争率が高かった(大学に行きたくても行けないという状況)。しかしその後の進学率のゆるやかな上昇は、大幅な人口減によるところが大きく、希望すれば誰でも入れる「大学全入時代」に近づいた。)
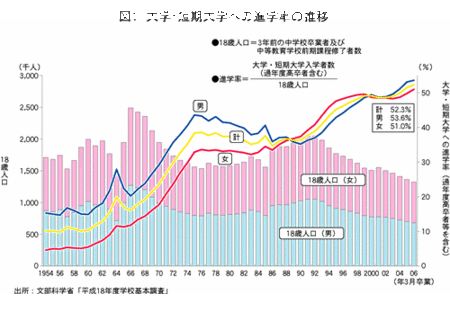
「学歴」は多くの人にとって微妙な問題であり、「今は学歴ではなく実力の時代ですよね」といった無難な言説がまかり通っている。だが本当にそうだろうか? 計量社会学者である著者は、大規模な社会調査の統計にもとづいて、学歴が日本社会の格差問題において果す役割を分析する。「実力の時代」とは言っても、大卒と高卒は当初から賃金水準が異なり、大卒は働く期間が4年短くても生涯賃金は1.2〜1.5倍も多い。つまり、学歴は社会の「公認の格差発生装置」なのである。一流大学間の優劣の品定めや、幼児の「お受験熱」といった表層的な話題は、人々の関心を引くネタになるが、大卒と非大卒の関係と社会におけるその役割分担という地味な問題は、あまり論じられることがない。マスコミでは「ニート」「フリーター」「ワーキング・プア」「派遣」「下流」などといった用語が活発に飛び交っているが、しかし著者によれば、その背景には、大卒と非大卒の間の「学歴分断線」が大きな役割を果している。大卒と非大卒が人口の半々で均衡し、それが固定化する社会、これが現代日本の新しい問題なのである。
高度成長期のしばらく後までは、進学率の上昇によって、子供の学歴が親を上回る「学歴上昇メリット」が多くの家庭にあった。それが「一億総中流社会」の明るさでもあった。だが今は、子が親より学齢上昇する家庭は、全体の四分の一以下に減っている。大卒の両親が増えた結果、その子供のうち3人に2人は大学に進学するが、1人は進学しない。子が20代の統計では、親が大卒・子が非大卒という「学歴下降家族」もすでに13%に達しているのだ。統計的には、親が非大卒・子も非大卒は38%、親が大卒・子も大卒は26%、親は非大卒・子が大卒は23%。この、13+38対26+23という非大卒と大卒のちょうど半々の均衡は、多くの要因の複合的な結果であり、日本社会のある種の成熟と固定化を表している。「大学全入時代」と言われるが、それはちょうど「ニート」が問題視される時期と同時であり、大学進学率が約50%強で頭打ちになっていることと関係している。今の高校生の半数は、そもそも最初から大学進学を希望しない。家庭の経済的理由もあるだろうが、なぜ50%強で頭打ちになるのか、その理由はよく分かっていない。
>大学への進学門戸の「バルブ」を全開にしても、進学希望者はせいぜい同年人口の50%程度しかいない。[文科省は]慎重に右肩上がりの傾きを調整してきたわけですが、結局大学進学率50%のところには、調整しなくても頭打ちになるような「ガラスの天井」があることが分かったのです。・・・どうしてそれが40%や60%ではなく50%なのか、その理由については、いまのところ確定的なことは分かっていません。(p26)
現状を理解するには、そもそも学校はなぜ存在しているのかという点から考えなければならない。かつての階級社会とは違って、近代の学校制度は、世代の交代に際して、社会における地位や価値を世襲とは異なる形式で再配分するために、人材を形成し割り振るシステムなのである。
>学校教育は、親から子への世代間の関係に対し、公的に定められた「フィルター」として介在することで、世襲制の社会にみられたような閉鎖的な関係を解消していくことをめざしていたのです。学校教育は、そこで培われた人材を、能力に合わせてそれぞれの持ち場に割り振って、人々に仕事やお金についての成功のチャンスを振り分けることを目的のひとつとしています。つまり、学校は元来一人ひとりの知識や技能に差をつけるためのものであって、学歴による差異には、社会の設計どおり発生しているという側面があるのです。いわば学歴は正規の格差生成装置なのです。(p33)
厳格な階級社会であるヨーロッパの大学は、その当初は上流階級の子弟の教育を目指すものであった。ヨーロッパの最上級の大学には、今でも、そうした上流階級の文化の香りのようなものが残っている。ところが明治以来の日本の大学制度は、すでに存在する上流階級に対応するものではなく、むしろ大学という手段を通じて広範な国民の中から人材を集め、社会の近代化を担う新しいエリートの階層を形成しようとするものであった。だから東大を頂点とする旧帝大の学生は、上昇志向だけは強いが、上流文化の「気品」をもたない大衆的な人間であった(p124)。このように日本では、学歴が社会における格差を意図的に作り出してきたので、今日の大学進学率の問題には、日本社会の構造的な多くの問題が集約的に表現されているのだ。
著者は、現在の「格差」論争や「下流」論争で曖昧に用いられる傾向のある「豊かさ」「格差」「不平等」という概念を相互に区別し、厳密に定義する(p78f)。「豊か⇔貧しい」という尺度は、社会全体の指標であり、一人当たりのGDPや大学進学率など、ある社会全体の水準を表すものである。それに対して「平準⇔格差」という尺度は、その社会においてある個人がどのような上・中・下の位置にあるかを示すもので、所得、資産、階級、階層などである。しかし「平等⇔不平等」という概念は、また違う。それは、量の差異の指標ではなく、こうした格差が発生する因果的メカニズムを、我々がフェアとみなすかアンフェアとみなすかという評価の視点である。たとえば、親の地位や所得が高いほど、子供が高い学歴を得たり、高い地位を得たりするのが「不平等」である。親子という自分の自由にならない関係によって、”社会における自分の地位”が決定されるということは、フェアとはみなされないからである。学歴の問題は、親からみれば子供の進学の問題である。子供にとって進学は、親の置かれた状況に大きく左右されている。つまり、「親と子の世代間の関係」において、どのような価値、地位、所得などが継承されるか、あるいはされないかという点で、学歴は社会の「平等・不平等」の重要なファクターなのである。[続く]