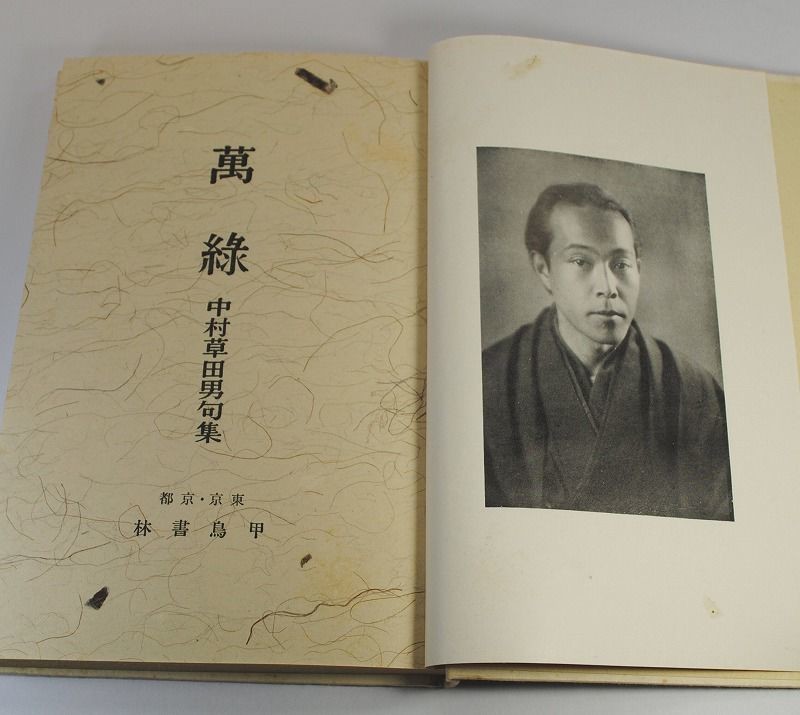[演劇] アイスキュロス/R.アイク『オレステイア』 新国立・中劇場 6月26日
(写真↓は、左から、クリュタイメストラ、イピゲネイア、エレクトラ、オレステス、アガメムノン、このメンバーが食卓を囲むことは、アイスキュロスにはなく、ありうるとすればエウリピデス『アウリスのイピゲネイア』だが、そのときオレステスは幼児のはず、2015年のイギリス上演では子役がやっている https://www.youtube.com/watch?v=dHE1V19Bz5Q)

イギリスの若い劇作家ロバート・アイクが、アイスキュロス『オレステイア』三部作を翻案劇というかミステリー劇に仕立て直した作品。だが、全体の構成が完全な無理筋で、私は見ていて白けてしまった。ほとんどの科白が浮いた感じで、リアリティがない。場面場面で、「えっ、そりゃないでしょ 」「人間は、そんな科白ぜったい言わないよ」という気持ちになる。翻案劇というのは難しい。まず本作は、全体がオレステスの裁判という枠組みで、精神障害で記憶を喪失しているオレステスに、女性の精神科医がいろいろ質問をして、過去にあった場面を想起させながら、裁判における事実認定を一つ一つ積み上げていくというプロセスをとる。しかし、その全体構造が分るのは最後であり、観客は、過去から現在まで時間の順にドラマが進んでいるかのように見せられるので、途中は分かりにくい。(写真↓は、エレクトラ、しかし姉エレクトラは実際には存在せず、オレステスの妄想が創り出した夢だった)

本作の構成が無理筋である理由は、大きく言って二つある。精神障害を起こしたオレステスに過去を想起させるという全体設定は、百歩ゆずって、仮によしとしよう(本当は、精神分析にしたのが、本作の最大の欠陥なのだが)。しかし、(1)姉のエレクトラを実在しない妄想としたので、母親クリュタイムネストラ殺しの「責任」の問題が、原作とまったく違ってしまった。たしかに刃物で手を下したのはオレステスかもしれないが、母をもっとも殺したかったのはエレクトラであり、だからこそ「エレクトラ・コンプレックス」といわれる母娘関係を表わす精神分析的概念にもなっている。母殺しは、オレステスの単独犯行ではない。(2) 次に、原作では、オレステスに母殺しを促したのは神アポロンであり、オレステスが自分の主体的判断で殺したのではない。そこを本作では、「印を読み取る」という「解釈」の主体としてオレステスを主体化し、アポロンの責任を曖昧にしている。アイクは、「オレステスは有罪なのか無罪なのか」と、近代世界の裁判と主体概念にもとづいて根本問題を立てているが、原作の焦点はそこではない。エウリピデス版『オレステス』では、死刑判決が出たオレステスに対して、アポロンが機械仕掛けの神として登場し、オレステスを赦す。アイスキュロス版では、同数だった評決にアテナ神が一票加えて無罪にするが、それでは怒りが収まらない復讐の女神たちを、アテナが必死でなだめ、おだてて、恫喝や説得をして、ようやく復讐の女神たちが怒りを収めるという場面が延々と続いて、それで終幕になる。つまりオレステスの有罪/無罪は本当の問題ではなく、恨みと復讐の連鎖をどこで止めるかが主題なのだ。本作では、最後にオレステスが、「アテナの一票で覆るのは、一人の人間が決めたということで、無罪であっても納得できない」とつぶやいて終幕になるが、もともと『オレステイア』はそういう問題ではないのだ。(写真下は↓、イピゲネイア(カサンドラ?)とアガメムノン)

とはいえ本作は、原作を離れて考えれば、いろいろと面白い想定がみられる。たとえば、イピゲネイアとカサンドラを同一役者でどちらも黄色い服を着せて、精神障害のオレステスの意識の中で二人は同一人物になっていると示唆したのは、なかなかいい。消えたイピゲネイアはカサンドラとなってアガメムノンのところへ戻るのか・・・。しかしまぁ、エレクトラも弟の妄想だったというのは、「それはないでしょ!」と言わざるをえない。イピゲネイアも子供っぽい仕立てで、どうも変。劇の科白の大部分が、精神分析の受け答えのような「自己解釈」が中心なので、鬱陶しくて空疎な感じになっており、原作と非常に違う雰囲気になった。「エディプス・コンプレックス」などギリシア悲劇は全体が精神分析的なのだが、しかしそれは、劇の中で人物が精精神分析まがいの科白をしゃべるということではない。アイクはそこを混同しているのではないか。精神分析は、分析医とクライアントの間だけの閉ざされた空間で、治療のために行われる。神父への告解が公開されないのと同じである。第三者の前で行われる裁判とはまったく違うので、語られる言葉の性格が異なるはずである。役者としては、オレステスを演じた生田斗真はとても瑞々しくてよかった。(写真下は↓、イピゲネイアとエレクトラ)

ごく短いですが、紹介の動画が。
https://twitter.com/endless_ss0704/status/1136833474353029120